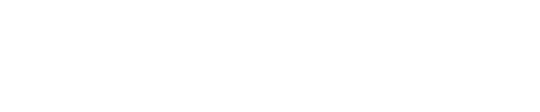MYP
ミドル・イヤーズ・プログラム
MYP(ミドル・イヤーズ・プログラム)は、国際バカロレア(IB)の中等教育課程にあたる5年間のプログラムであり、11歳から16歳までの生徒を対象としています。MYPの課程を修了することで、生徒は探究的で国際的な視野を持った学習者としての基盤を築き、将来的にDP(ディプロマ・プログラム)などの高等教育課程に円滑に移行できるよう設計されています。
MYPは、知識の習得だけでなく、学んだことを実生活に応用する力を育むことを重視しており、学習者に対して「概念理解」「グローバルな文脈」「学習者像(Learner Profile)」の3つを柱とした教育を提供します。さらに、生徒はすべての教科で評価基準に基づいた多面的な評価を受けるとともに、「パーソナル・プロジェクト」と呼ばれる個人探究課題に取り組みます。
国際バカロレア機構(IBO)は、2024年10月時点で、世界160以上の国と地域において約5,900校を認定しています 。日本国内では、2024年12月31日時点で、IB認定校および候補校の合計が251校に達しています 。そのうち、学校教育法第1条に基づく正式な学校(いわゆる「1条校」)は81校となっています 。

特別の教育課程の実施状況等について
(1)特別の教育課程の概要
名古屋国際中学校では、英語力上位層を対象とした「インターナショナルクラス」において、国際バカロレア(IB)ミドル・イヤーズ・プログラム(MYP)の理念に基づいた特別の教育課程を編成しています。英語・理科・音楽・道徳・総合学習などの授業を、ネイティブインストラクターがすべて英語で行うことで、探究的な学びと多文化理解を促進しています。また、本校のインターナショナルクラスは、併設の名古屋国際高等学校と連携し、高校1年生がMYPの最終年(MYP5)にあたる形でプログラムを継続しています。これにより、生徒たちはIBディプロマ・プログラム(DP)へと円滑に進学できる環境が整っています。さらに、MYPの「Design」の学習内容を、高校課程の「情報Ⅰ」に読み替えることで、日本の教育制度にも適合した柔軟な学びを実現しています。
(2)学校又は地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要性
グローバル人材の育成がますます重要視される中、名古屋国際中学校・高等学校では、中高一貫教育を通じて、生徒の国際的素養の涵養に力を入れています。MYP(ミドル・イヤーズ・プログラム)の導入は、本校が掲げる以下の「5つの能力」の育成方針と合致しており、生徒が将来、国際社会で主体的に活躍するための基礎を築く教育プログラムとして位置づけています。
Ⓐ グローバルな課題を科学的・論理的に思考できる
Ⓑ 課題を探究するためにコミュニケーションできる
Ⓒ グローバルな課題を協働して解決しようとできる
Ⓓ 課題を探究するために情報を的確に活用できる
Ⓔ 課題探究の進行の管理や振り返りができる
本校は、2023年にMYP(ミドル・イヤーズ・プログラム)の認定を受け、以来、国際バカロレアの理念に基づいた教育実践を着実に積み重ねています。
(3)特別の教育課程の実施状況に関する把握・検証結果
教育課程表及びシラバスに基づき、おおむね計画通りに実施している。
探究型学習の評価指標や課題設計の継続的改善が求められるが、生徒の反応や成績推移から一定の成果が認められている。
(4)保護者及び地域住民その他の関係者に対する情報提供の状況
保護者説明会や公開授業、定期的な学校通信を通じて、インターナショナルクラスおよびMYPの教育内容を発信している。
実施の効果及び課題
(1)教育目標との関係
MYPによる特別の教育課程は、本校の教育理念である「21世紀のグローバルリーダーに求められる資質の育成」と高い親和性がある。思考力・コミュニケーション力・探究力・自己省察力など、生徒が中学生段階で身につけるべき能力を体系的に育成できる教育課程となっている。
(2)実施による教育効果の検証
生徒による授業評価や探究課題の提出状況からは、以下のような効果が見られている。
・生徒の英語運用能力と課題解決能力の向上
・プレゼンテーションやグループワークにおける積極性の向上
・探究型学習(Inquiry-Based Learning)への関心の高まり
学校評価アンケートのMYPにおける授業の満足度
(5.0満点)
・2024年度 3.43
・2025年度 3.87
課題と今後の方向性
・英語教材及び参考資料の整備
MYPで使用する英語教材や探究課題に対応した参考資料が不足している。
→ 洋書や学術データベースへのアクセス環境を整備し、教育内容のさらなる充実を図る。
・教員の指導力向上
MYPに関する指導力の強化が求められている。
→ IBワークショップへの参加や校内研究を推進し、教員の専門性を高めていく。
・評価基準の透明化と共有
探究課題における評価の透明性が課題。
→ 評価基準を明確にし、生徒・保護者への説明を丁寧に行うことで、学びの納得感と学習意欲の向上を目指す。
・評価基準の整合性確保
IBのガイドラインに従い、原則として成果物の評価は標準化されている。
→ 今後は、MYPの評価規準(4観点)を文部科学省の3観点(知識・技能、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度)と対応させるための手順をより明確にしていく必要がある。