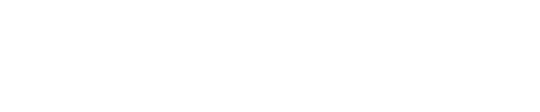SGH国際理解研修
国際理解研修SGHコース紹介
高校2年次のSGH国際理解研修の概要をご紹介します。
各コースが本校のSGH活動の3分野に対応し、それぞれ特色のある研修内容となっています。
国際理解研修の事前学習および研修後の発表などを通し、探究学習の充実を図ります。
| フィリピン | オーストラリア | マレーシア、シンガポール | |
|---|---|---|---|
| 時期 | 6月下旬〜7月初旬 | 7月中旬〜8月末 | 11月下旬 |
| 期間 | 2週間 | 6週間 | 5日間 |
| 学科 | 普通科(中高一貫コース) | 国際教養科、普通科(中高一貫コース) | 普通科 |
| 視点 | 経済的視点(経済活動と貧困) | 社会文化的視点(多文化共生と減災) | 環境的視点(社会生活と循環) |
| 概要 | 主に貧困問題とその解決をテーマにフィリピンのストリートチルドレンとの交流や、貧困問題の現実を様々な面から体感します。驚きとともに視野が広がり帰国後、ボランティア活動に自発的に参加する生徒が多いことも特徴です。 | 多文化共生をテーマに様々な異文化を理解・共存する為の見識を学びます。現地大学での研修と、現地高校での高校生同士の交流を経て、生徒たちは大きく成長します。 | 環境をテーマにシンガポールの水資源を例に循環型の社会、社会の持続可能性を考えるコースです。期間は短いですが、日本との比較などから、多くを学べるコースです。 |
マレーシア・シンガポールコース(2017/11/20~24)
11月20日から24日にかけて高校普通科2年生の国際理解研修を実施しました。このコースは質素な文化(マレーシアの村)と栄えた文化(シンガポール)という両極な異質文化を体感できることが特徴です。主にはマレーシアの村でのホームビジット、NUS(National University of Singaporeシンガポール国立大学)における研修、シンガポール市内観光、水の学習、セントーサ島での自由行動が挙げられます。特にNUS研修は今年度初めて取り入れたもので「シンガポールの歴史」「NUSの歴史と意義」の2つの授業を受けました。総合学習でこの授業の事前学習を行なった効果があり、生徒達は興味深く授業を聞いていました。ホームビジットでは現地の民族衣装を着て美味しいマレー料理を食べ、マリーナベイサンズからの絶景に驚嘆し、ナイトサファリの大迫力に興奮した様子でした。密度が濃い5日間の研修を通して、海外の生活や文化を十分に体感でき、多国籍の人との交流を深め、研修の目的は十分に達成できたと思います。
オーストラリアコース(2016/7/15〜8/26)
オーストラリアのシドニーで行われた国際理解研修に18名の生徒が参加しました。研修は2部構成となっており、前半の3週間は異文化理解学習として、マッコーリー大学にて「多文化共生」を軸としたアクティブ・ラーニング形式のプログラムを実施しました。生徒たちがホームステイを通じて体感する食文化や、オーストラリアの先住民であるアボリジニの文化など現地で実際に触れることで生きた国際感覚を養います。そして、3週間の学習の総仕上げとして、現地で生徒が興味を持った異文化について英語でプレゼンテーションを行いました。後半の3週間はグループ毎に現地高校へ通いました。ここでのホストファミリーは現地校生徒や教員であり、一度の海外研修において二つの家庭でホームステイを経験することも、異文化理解を深める貴重な機会となっています。同年代の外国の学生がどのような日常生活を送っているのか経験し、趣味や若者文化などに国籍や生活圏を越えて共感を抱くこともまた多文化共生の学びに欠かせないものといえるでしょう。
フィリピンコース(2017/6/25〜7/10)
普通科(中高一貫コース)5年生を対象にフィリピン・マニラにおいて国際理解研修を行いました。約2週間の本研修では、貧困問題を中心とする社会課題を学習します。
マニラ中心部で路上生活をしている子ども達の生活環境や郊外のごみ山を視察しました。また、子どもの保護施設や更生施設を訪問し、入所している子ども達と「理想の社会」について考える交流活動を行うことで、生徒と子ども達の間に非常に深い絆が生まれました。次に、現地の高校を訪問し、現地の高校生と共に授業を受け、お互い自国の料理を実際に調理して紹介しました。また、ダンスや民族衣装なども互いに発表し、異なる民族・文化に対する理解を深めました。さらに、キャリア教育の一環として、独立行政法人 国際協力機構(JICA)フィリピン事務所や日本航空株式会社(JAL)マニラ支店、NPO法人ユニカセ・ジャパンが経営するレストランなど、フィリピンで活躍する日本人や日本企業を訪問しました。海外の現場で実際に働いている方や社会起業家の方と直接対話することは、生徒が自らの将来を考えるための良い機会となりました。
これらの経験から学んだことを生かし、今後アウトリーチ活動として文化祭でフェアトレード商品の販売学習や研修報告会を行い、フィリピンが抱える貧困や経済格差、災害などの社会問題の現状を広く伝えていく予定です。
マレーシア・シンガポールコース(2016/11/21~25)
本校SGHの「社会生活と循環」に関わる取り組みとして、マレーシア・シンガポールにおける5日間の海外研修プログラムを行いました。水資源に乏しいシンガポールにおいて「水」をテーマに持続可能な社会について探究学習を実施しました。
本研修では水資源に関する多面的な事前学習を行いました。飲み水を確保する重要性を学習した後、雲を発生させる科学実験を行い、真水が生成されるメカニズムについて学習しました。また、シンガポール人で日本在住のソーシャルアントレプレナーであるデニス・チア氏を講師にお招きし、シンガポールの歴史や多民族国家特有の文化・社会についてご講演頂き、生徒との交流も行いました。事前学習の小括として学習内容をクラスで議論し、壁新聞にまとめて校内に掲示しました。
現地では、事前学習に基づき4つの水源(輸入水のパイプライン、海水の淡水化技術、再生水施設、ため池)について実際に見学し、生徒たちは日本とは地理的・経済的に異なる環境を実感しました。
オーストラリアコース(2016/7/16〜8/27)
本校SGHの「多文化共生と減災」に関わる取り組みとして、オーストラリア・シドニーにおける6週間の海外研修プログラムを行いました。
研修内容は3週間ずつ前後半に分け、前半の3週間はマッコーリー大学で実施されました。『多文化共生』をキーワードとしたアクティブラーニング形式の学びを通じ、「日豪の文化の違い」、「モノカルチャーとマルチカルチャー」、「先住民と差別」等のトピックについて理解を深めました。生徒は現地滞在中、常に周りの事象を論理的・批判的に捉えることを意識し学習を進め、まとめとして『多文化共生』に関するテーマについてプレゼンテーションを行いました。このプレゼンテーションの様子は、日本でSGH活動を行う後輩たちにライブストリーミング配信され、現地での学びを国内の生徒へ還元しました。
後半3週間は、7つの高校に分かれ、現地の高校生活を体験しました。前半期間で学んだ多文化共生社会を実感する3週間となり、帰国時の生徒の表情はみな自信に満ち溢れ、今回の研修での成長を思わせるものでした。
フィリピンコース(2016/6/26〜7/10)
本校SGHの「経済活動と貧困」に関わる取り組みとして、フィリピン・マニラにおける約2週間の海外研修プログラムを行いました。研修では、現地の高校、子供の保護施設、日系企業の見学・交流を通して、貧困問題を中心とする社会課題について学習します。
最初に本校の協定校であるラサール高校や現地の高校を訪問し、現地生徒との交流会、授業参加、調理実習、昼食会、文化発表会を行いました。生徒は文化交流の一環として日本の浴衣と甚平を紹介し、日本の文化を伝えました。さらにソーラン節を披露し、盛況のうちに現地との交流を深めることが出来ました。
次に、路上の子ども達との交流とゴミ処分場を訪問し、マニラの中心地近くで、路上生活を送る子ども達の生活圏を見学しました。ドロップインセンター(子どもの一時保護施設)や子どもの家(子どもの長期保護施設)、路上で生活をしていた青年の自宅などを見学し、実際にそこにいる子ども達と2泊3日の合宿を通じて交流を行いました。合宿では、「One Dream One Voice One Action」のスローガンのもと、国や言葉の壁を越え、お互いのことを話し、共に「理想の地域」について考えることで、生徒と子ども達の間に非常に深い絆が生まれました。生徒達は合宿期間中、主体的に行動し、子供達とコミュニケーションを取ろうとタガログ語にチャレンジするなど、積極的な姿勢を見せてくれました。
さらに、キャリア教育の一環として、フィリピンで活躍する日本企業を訪問し、社員・職員方にお話を伺いました。独立行政法人 国際協力機構(JICA)や日本航空株式会社(JAL)で働いている方や社会起業家の方との交流、職場体験は生徒にとって将来を考える良い機会となりました。
帰国後は今回の経験から学んだことをアウトプットする活動として、現地で買い付けたフェアトレード商品を文化祭で販売し、フェアトレードの普及と、経済格差や貧困について調べたことを紹介しました。